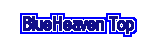
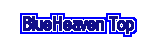 |
蒼き虎の伝説Final Fantasy XI オリジナル小説 written by Lygia |
Back | Novel Top page | Next |
第2章 青い瞳の召喚士〜リムーサ
雪のやむ事のないと思われるズヴァール城外郭では、サンドリア王国・バストゥーク共和国・ウィンダス連邦、そしてジュノ公国の4国で編成された連合軍が、デーモン族との戦闘を繰り返していたが、尽きることのない戦闘に、兵士たちは、疲労の色を濃くしていた。 前線には、簡易テントやコテージが、いくつか、しつらえられており、その中でも、将軍たちが軍議を行うコテージは、一回り大きく、設置されていた。 「ノーグの使者というのが、来るというのは、今日だったか?」 今回のバストゥーク共和国からの遠征軍を率いて来た、将軍スカーレット・ヘアードは、参謀であるヒュームのカツリョウにたずねた。 将軍スカーレット・ヘアードとは、ヒュームから命名された名前であり、本人は、自らを『ウール』と呼ばれることを、好んでいた。 「この膠着状態を打開するために、ジュノの大公が呼び寄せた部隊ですね。実際は、ノーグ出身の隠密部隊ということらしいですが……もう日が暮れようというのに、遅いですね…ウール将軍」 参謀のカツリョウも、いらいらを隠さずにウールに応えた。 「確か、アヤメもノーグの出身だったな……ちょっと呼んで来てはもらえないか?」 「わかりました……彼女は、まだ最前線で戦闘しているはずなので、呼び戻すには時間がかかるとは思われますが……すぐに、伝令を出しましょう」 カツリョウは、脇に控えた伝令部隊の1人に、耳打ちをした。 「ノーグの使者が来たら、城の内郭まで割って入ることにするか…」 ウールは、独り言のようにつぶやいて、目の前に広げられている、ズヴァール城の内郭と外郭の地図に目をやった。 「ところで、ウォルフガング殿……あなたは、ノーグの使者というのが使い物になると思われるか?」 ウールは、ジュノ公国の代表である、ウォルフガングに聞いた。 「わたしも、どのような部隊が来るのかは知らされていませんよ」 ウォルフガングは即答した。 「ジュノの兵士たちは、この膠着状態をどう打破しようと考えておられますか?」 ウールは、重ねて聞いた。 「ジュノの兵士たちに命令を下すのは、わたしだが、すべての国の意見が一致しないことには、次の手を打つことはできない。ジュノの軍隊は、バストゥークやサンドリアほどの規模はないですから……バストゥークが独断専行するのであれば、止めはしませんが、やはり、ウィンダスもサンドリアもノーグの使者を待ってるというのが、正直なところでしょう。特にウィンダスのシャントット殿は、今回の遠征では、指揮を執っているのかいないのか……まったく軍議にも加わらないし……」 「まぁ、あのご婦人の気まぐれは、今に始まったことでは、ないからな」 ウールとウォルフガングは、お互いの苦笑いの表情を確認して、さらに皮肉な笑みを口辺に浮かべた。 「では、ノーグの使者が到着したら、軍議を再開しましょう。わたしは、ちょっと兵士の様子を見てきます」 ウールは、ウォルフガングに言い残すと席を立った。 ちらつく雪は、まだ降り続いていた。 30分ほど時間が経過したところで、ウールの前に、黒髪のヒュームが、足音一つたてることなく、姿を現した。アヤメであった。 「おう…忙しいところ、呼びつけてしまって失礼をした…前線の様子はどうなっているか聞きたかった」 「前線は、相変わらずです」 アヤメは、短く答えた。 「実は、到着が遅れているノーグの使者について、お前の意見を聞きたかったのだ。お前もノーグの出身だと言ってたな。どのような部隊が編成されているか、おおよその見当くらいはついているだろう?」 「情報は得ております…」 「なに?なぜ、報告しなかった?」 「聞かれなかったですから…」 アヤメは、顔色一つ変えずに、答えた。 「そうだったか……では、その情報というのを、俺に報告してくれ」 「はい…この場でよろしいですか?」 「ああ、かまわぬ…仮に、デーモンの斥候に聞かれたとしても、やつらには、どうしようもないだろう…他国の者たちには、むしろ聞かせてやりたいくらいだ。すべての国が揃ってから、作戦を確定させようなどと…どの国も、守りの戦闘には力を発揮するが、こういった攻めの戦闘には、どうも、積極性がなくて困る」 「わかりました。まず、兵を率いるのは、リムーサと名乗る召喚士です。部隊は、その隊長指揮下の12人が、こちらに向かっています」 「召喚士?」 「はい……部隊の兵は、召喚術に長けた忍者たちです」 「いつごろ、着くか、わかるか?」 「もう、まもなく着くでしょう……」 「お前は、そのリムーサという者には面識があるのか?」 「何度かは……ノーグに派遣された時に、会っています……それと、バストゥークでも……」 アヤメは、言葉を続けようとしたのか、口元をかすかに揺らしたが、その後の言葉を飲み込むように口を噤んだ。 「ところで、アヤメ……お前は、この遠征について、どう思う?」 「どう思うとは?」 「うむ……今回の遠征の目的は、力を付けつつある獣人たちの力を削ぐことが目的であることは、既に説明してあったはずだが、実は、どの程度までの攻撃を加えるかについては、他の国との協議の上でという説明を大統領から受けたに過ぎないのだ。しかし、その他の国との軍議も、ここに前線を張ってから、すでに10日余りが過ぎ、いっこうに目的がはっきりとはせん。他の国に問い詰めれば、『ノーグの使者を待とう』の一点張りだ。どれほどの能力を持つ指揮官かは、わからないが、これ以上の無策のにらみ合いは、兵士の指揮にもかかわる。お前も、そうとう、いらついているのではないのか?」 「リムーサが到着すれば、駒が揃うということでしょう。特に、あの女は、シャントットのお気にいりですから……」 アヤメは、にこりともせず、そう言った。 「シャントットのお気に入りとは…なぜ、そのようなこと、お前が知っているのだ?」 「さきほど申し上げましたとおり、あの女とは、面識があります。所属する国が違うので作戦を共にしたことはないですが、それなりの力を備えた召喚士であることは間違いないです。わたしは、好きませんが……」 「そうか…なぜ、好かぬ?」 「それは……あの女が、どう戦うか知れば、わかりますよ……シャントットの好む戦い方をするのは確かです」 アヤメは、ウールの視線から、顔をわずかに背け、唇を噛んだ。 「では、ウール将軍…兵士の指揮をしなければなりませんので、持ち場に戻ります。軍議の結論が出ましたら、伝令により知らせてください。失礼いたします」 アヤメは、ウールに対して、いつもの略式の礼をすると背を向け、小走りにズヴァール城の最前線のほうへと向かっていった。 (日没までは、およそ1時間くらいか……それまでには、来るのだろうな) それから1時間後…ウールたちの待つコテージに、一人の青いダブレットと青いマントを身にまとい女装したヒュームが到着した。強いウェーブのかかった髪を青く染め、その瞳の色も、やはり青かった。 ウールも、30分ほど前に、ノーグの使者の到着が間もなくとの伝令を受け、コテージに戻って来ていた。既に、そこには、ジュノの代表であるウォルフガング、サンドリアの代表であるトリオン王子、そして、随行してきていると聞いてはいたが、いっこうに姿を現さなかった、ウィンダスの代表である、3賢者の一人、シャントット博士が、それぞれに参謀クラスの者を連れて席に着き、ノーグの使者が到着するのを待っていたのだ。 「人選に手間取り、到着が遅くなったことを、まず、お詫びいたします」 青い瞳のノーグの代表のはじめの言葉は、若すぎる声による謝罪の言葉であった。 「リムーサ……人選に手間取るのは、いつものことでは、ありませんの?これくらいの遅延、覚悟しておりましたわよ。とりあえず、これで、駒は揃いましたわ……作戦を告げますわよ」 今回のウィンダスの代表である、シャントット博士が、いつもの横柄な口調で、会議の進行を取り仕切るように言った。 「む…作戦とは…今まで、軍議にも顔を出さず、ようやく現れたと思えば、この場を取り仕切るような口ぶり…シャントット殿…わたしは、我が国王から博士の言葉に従えなどという命令は受けておりませんぞ」 髪を逆立てて、サンドリアのトリオン王子が、不平を露わにした口調で、シャントットをにらみつけた。 兵法書を熟読しているわけでもないトリオン自身は、こと戦略に関しては、魔法などを使用しない、力と力のぶつかりあいによる戦いの指揮を採ることが常であった。であるから、今回のような攻城戦のような、複雑な作戦を必要とする遠征については、シャントットの軍議への参加を心待ちにしていたのは、確かだったのだ。しかし、いつにも増して、あまりにも横柄な態度に何か言わずにいられず、言葉を発した。 「ほう……?では、人海戦術しか知らないサンドリアが、なにか戦略を用意してると言われるのですか?トリオン王子どの…てっきり、わたくしは、この、ヴァナ・ディールで一番と言われる、わたくしの頭脳に頼りきっているのかと誤解してましたわよ……ほんとうにサンドリアに、この戦闘についての戦略があるというのなら、うかがいたいものですわ」 シャントットが余裕たっぷりに、さらにトリオンをからかうような口ぶりで、艶然と笑いかけながら言い放った。 トリオンとしては、自身の心の内をシャントットに見透かされていたのは間違いなかったので、咄嗟に返す言葉も浮かばず、唇を噛んだ。 「図星……ということですわね」 「く……」 「トリオン殿……相手も、相当の魔法の使い手が配置されています……シャントット殿の軍議への参加を待ち望んでいたのは確かなのですから……ここは、シャントット殿の作戦を伺いましょう……特に、今回のノーグからの使者については、シャントット殿が、よくご存知のようだ」 軍議を進めたいウールが、2人のやり取りに業を煮やして、トリオンをまっすぐ見つめ、そう言った。 「バストゥークの代表殿が、そう言われるなら……シャントット殿の意見を伺いたい」 トリオンは、搾り出すように言って、椅子に座りなおした。 「では……とんだ邪魔が入りましたが、今回の作戦を告げますわよ」 シャントットは、相変わらず余裕たっぷりの笑みをたたえた顔で、自分が立てた作戦を話し始めた。 「このズヴァール城では、敵が外郭に雑魚を配置してあるのは、みなさんご存知ですわね?この雑魚に阻まれて、内郭まで進入できませんのが、今の状況ですわ……まぁ、わたくしが侵入して、様子を調べてくることなど造作もないことなのですが、ここに到着したノーグの13人の忍軍は、侵入・偵察をもっとも得意とするものたちですわ……ですから、わたくしの代わりに、この者たちに、内郭への調査をさせます」 「わたしと部下12人で、内郭の状況を調べてきます。3日間の時間をください」 シャントットからリムーサと呼ばれたヒュームの女が、会釈をしながら言った。 「3日の間、リムーサたちに内郭の状況を調べさせます……その間、外郭の敵との小競り合いは、今まで通り続けていただきますわよ。敵に指示を出してるのは、おそらく、獣人たちの、それぞれの種族を統べる7将軍と思われます……偵察が済み、突入部隊が内郭に突入したら、この将軍たちの親衛隊と、それぞれの将軍を分断しますわ……そして、親衛隊を分断した将軍に対するのは……バストゥークのウール将軍率いる最精鋭部隊……もっとも危険な獣人たちではありますが、1対1の戦闘においては、ウール将軍を凌ぐ者は、この遠征軍には見当たりませんから……敵の親衛隊は、ウール将軍の一騎撃ちが終わるまで、わがウィンダスの魔道士部隊が、全力を注いで、その力を無力化させておきます。どちらにしても、内郭に、すべての部隊を突入させるわけにはいきません。各エリアの将軍を倒し、制圧したところに随時、前線を移動させますわ」 「ウール将軍に、7人の敵将軍すべてを、まかせるというのか?将軍の力量を低く評価しているわけではないが、リスクが大き過ぎはしないか?」 トリオンが、シャントットの言葉が途切れたところで、口を挟んだ。 「トリオン殿が率いるサンドリア軍には、ジュノの軍とともに外郭の敵の足止めをしていただく必要がありますわ……外郭の敵が内郭に入り込み…挟撃された場合、この作戦の成功率は極端に下がることになると思われます。駒が少ないのは、初めからわかりきっていることですわ。万一、ウール将軍が倒された場合は、そこで兵のすべてを引き上げさせます。とにかく、敵の7将軍の配置がわからないことには、攻略の手順を決めることはできませんわ……リムーサ……わかってますわね?わたくしが、あなたに、どれほどの期待を抱いているか……1年前のような、みっともないことを今回も繰り返すようならば、ノーグのギルガメッシュに、きびしく報告をすることになりますわよ」 「わかっています……博士……博士に拾っていただいた恩に報いるためにも、今回の作戦、必ず成功させるよう、働かせていただきます」 青い瞳の召喚士は、静かにそう言った。 「ウール将軍が突入するときには、あなたも、部隊を率いて将軍の盾となることです。偵察と突入部隊への道案内は、あなたの役目ですことよ。リムーサ」 「心得ています」 「いざというときは、蒼き虎をためらわず使いなさい……それと、ウール将軍……リムーサの率いる小隊の指揮は、あなたに任せることにしますわ。作戦行動中の報告は、ウール将軍と、わたくしに漏れなくするよう……よろしいですわね」 「心得ています」 「サンドリア軍への報告とジュノ軍への報告は、リムーサの報告を取りまとめた上で、わたくしから、前線の指揮官に伝えますわ……トリオン殿、くれぐれも血気にはやって、外郭の敵を背走させることのなきよう、お願いしますわ。われわれの兵を消耗させることなく、ピンポイントで、獣人の指揮を執る将軍たちを暗殺していくのが、今回の作成の要ですことよ……トリオン殿、そして、ウォルフガング殿」 「今回は……あなたの作戦に従いましょう。わたしたちも兵の消耗をさせたくはない」 ウォルフガングは、トリオンが答える前に、答えた。 「うむ……そうだな。しかし、その召喚士が、どれほどの力を持つものかは、わたしも納得する材料は示してもらってはいないのだが……その偵察の報告内容によっては、作戦の変更の用意もしていただくことになるでしょう……が、とりあえずは、ノーグの使者のお手並み拝見ということにしておきましょう」 「では、リムーサ……今から、あなたたちは、ウール将軍の指揮下に入ることになります。よく、将軍と話し合い、作戦の成功を確実なものとするよう……よろしいですわね」 軍議は、そこで解散ということになった。 ウールは、リムーサを伴って、コテージから外へ出た。 バストゥーク軍のコテージに戻ったウールは、リムーサと前線から呼び寄せたアヤメを前に腕を組んで座っていた。 「たしか、おまえたち2人は、面識があったはずだな」 「はい……アヤメさまには、バストゥークに滞在した折、とても、よくしていただきました。とても、暖かいご家庭で、カエデさんという妹さんとは年が近いこともあって、何度か、一緒に遊びました」 リムーサは、先ほどの軍議の席での硬い表情がわずかながら取れて、若い娘特有の笑顔を作って、ウールに答えた。 「シャントットのところでは、家庭の味など、なかっただろうからな」 「はい……とても厳しい先生でした。もっとも、もともと弟子を育てるなどという、お気持ちなどは、ない方でしたので……」 「だろうな……ところで、なぜ、召喚士になどなったのだ」 「言わないと、いけませんか?」 「ああ……是非、聞きたいものだ」 「それは……きっと、一人でいるのがつらかったからかもしれません。召喚士ならば、いつでも、獣を呼び出すことができますので、退屈しなくて済むのではないかと……そんな思いで始めたように思います。もっとも……」 「もっとも……?」 「一人ぼっちでいることには、変わりは、ありませんでした」 「一人ぼっちは辛いのか?」 「はい……とっても」 「しかし、ノーグの使者として部下を率いているのであろう?それなりに部下とは親密になっていたりはしないのか?俺も、部下を連れて、よくバストゥークの町を飲み歩いたものだが、おまえとも、この作戦が済んだら、バストゥークの町で飲み明かしたいものだ……酒は、飲めるのだろう?」 「いえ……飲んだことは、ありません。わたし、まだ15歳です」 「若いとは思っていたが……15か……まぁ、飲めないこともないだろう……明日の作戦がなければ、酒を用意させるところだが、さすがに今はまずいな」 「もちろんですよ……将軍……若い娘と見ると、『酒、酒』って、それしか言わないんだから、困ったものです」 「アヤメさまも、よく誘われるのですか?」 「そりゃ、よく…なんてもんじゃありません。しょっちゅう」 アヤメは、うんざりしたような顔を作りながら、悪戯っぽく笑って言った。 「そうなんですか?」 「そうですよ、ウール将軍の女好きは、常軌を逸してます」 「おい、そこまで言うことはないだろう……俺だって、相手を見て口説いてるつもりなのだから……」 「やっぱり、わたし、口説かれていたのですね……」 リムーサが、そう言いながら相好を崩した。印象的な青い瞳から、ウールへの警戒色が多少薄まっているのが、なんとなくウールにも伝わった。 「あはは……まぁ、ガルカといえど、美女には目がないからな」 「では、わたしは、明日の偵察がありますので、そろそろ失礼いたします。仲間たちへも、今回の作戦について知らせないといけませんので……ウール将軍への報告は、レッドバードという者が勤めます。明日、偵察の前に、すべての仲間をウール将軍に紹介いたしますが、早朝でも、かまわないでしょうか?」 「俺は、今すぐでもかまわないが、お前も、部下への説明が必要なのだろう。明日の早朝で、まったくかまわない。ここで待ってる」 「恐れ入ります……では……」 リムーサは、丁寧にお辞儀をすると、ウールたちのいるコテージから退出していった。 翌朝、ウールの前に、リムーサが、12人の部下を連れて、現れた。 そして、昨日、ウールの前で見せたのとはまったく違う表情で、事務的に、部下たちの紹介を始めた。 「今回、わたしと行動を共にする仲間です。ノーグからの使者は、わたしを含め、すべてバストゥークのウール将軍の指示の下、行動することとなります。まず……すべての者がそれぞれ能力の異なる獣を召喚する能力と高い忍びの能力を有しています」 リムーサは、部下の忍者12名の名と、操る召喚獣の特徴を、ウールに告げた。 無数の敏捷なる鼠を操る者…グレイラット、 鋭い角を持つ雄牛を操る者…パープルバッファロー、 無音の行動を得意とする虎を操る者…ホワイトタイガー、 保護色による隠密行動を得意とする兎を操る者…レインボーラビット、 破壊の炎を使う竜を操る者…ブルードラゴン、 強力な毒蛇を操る者…ブラックスネーク、 翼を持つ馬を操る者…スカイブルーホース、 睡眠能力の突出した羊を操る者…グリーンシープ 知恵が発達し魔法を得意とする猿を操る者…シルバーモンキー 高速度で飛び廻る鳥を操る者…レッドバード、 精密な作業を的確にこなす犬を操る者…ウルフドッグ、 そして、戦闘能力の秀でた猪を操る者…ワイルドボア 「これが、特殊任務用に編成された、わたしの仲間たちです。わたしを含めたすべての者が、ウール将軍を助け、今回の遠征の成功を果たすために、それぞれの持てる力を最大限発揮して、獣人の城の戦力を削ぐために戦います……それでは、リムーサ以下、13名、ズヴァール城へ偵察のため、これより侵入いたします」 「わかった……報告は逐一、良い報告も悪い報告も漏らさずに伝えてくれ」 ノーグ部隊の敬礼に、敬礼で応え、ウールは、リムーサたちを送り出した。 To be continued....... |
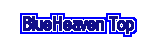 |
蒼き虎の伝説- Final Fantasy XI オリジナル小説 written by Lygia | Back | Novel Top page | Next |